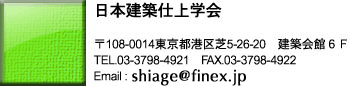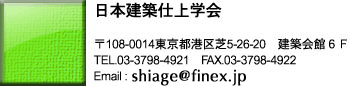| 1.投稿の形態 |
|
(1) |
提出原稿(本文・要約を含む)は版下原稿を原則とする。 |
| (2) |
版下原稿とは、そのまま製版できるように割り付けした原稿であり、パソコン(ワードプロセッサ)で作成し、版下用図・表・写真等を貼り込んだもの。 |
|
なお、図・表・写真はモノクロを原則とする。 |
| 2.原稿の書式・規格と論文等の構成 |
| (1) |
書き方種別と頁数
論文、報告および質疑討論の書き方種別と頁数は表1の通りとする。
表1
|
区分
|
論文・報告
|
質疑討論
|
|
書き方種別
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
本文種別
|
和文
|
和文
|
英文
|
和文
|
英文
|
|
要約種別
|
なし
|
英文
|
和文
|
なし
|
なし
|
本文・英文要旨・
キーワード基準頁
|
5頁以内
|
5頁以内
|
5頁以内
|
2頁以内
|
2頁以内
|
|
英・和文要旨頁数
|
−
|
2頁以内
|
2頁以内
|
−
|
−
|
|
超過頁
|
3頁以内
|
3頁以内
|
3頁以内
|
認めない
|
認めない
|
[注]各記入事項の字数・語数の制限は各項目の項を参照すること |
| (2) |
原稿規格と組み方
a)原稿用紙はA4サイズとし、原稿用紙1枚が論文集の1頁に相当する。
b)余白は天地30mm、左17mm、右16mmとする。
なお、第1頁最上段欄の「発行年月日」、「通しノンブル」および論文末尾の「原稿受理日」は採用決定後、本会で貼り付ける。
c)1頁は和文の本文相当で3000文字とし、本文は2段組を原則とする。
1行当たり30文字で1頁は50行2段組み、段間は2字空きとする。
(30文字×50行×2段=3000字)
従って、第1頁目は、表題・氏名・英文要旨・キーワード・所属機関等の記載分だけ本文記入量が削減されるので、2頁目から本文3000字とする。
d)書き方種別C・E(英文)およびBの場合の文字数・行換算方法は、1頁当たり800語とし、本文は1段組みを原則とする。 |
| 3.文字等の種別と印刷製版品質 |
| (1) |
所定枠内記入と鮮明な印字・作図
本文・図表等の記載事項は所定の記述スペースの枠内に鮮明に、かつ印刷版下として十分な濃度で記載するか、または別に作成した版下を貼り付けること。 |
|
(2) |
印書に使用する機種
パソコン(ワードプロセッサ)を使用する場合には、400dpi以上で印字が行えるプリンタとする。 |
|
(3) |
文字種別と大きさ
a)本文および注・参考文献の文字種別は、和文の場合は明朝体、英文の場合は和文用と同じフォントを原則とする。
b)本文および注・参考文献の文字の大きさは次による。
「和文本文 8ポイント」、「英文本文 8ポイント」、「注 ・参考文献 8ポイント」
c)章・節の表題文字は本文と同じ大きさとし、ゴシック体(またはワープロの強調文字)とする。
d)表題・氏名・所属機関等の文字の大きさは次による。
「和文表題 16ポイント、副題 11ポイント」
「英文表題 10ポイント、副題 8ポイント」
「和文氏名 10.5ポイント」、「英文氏名 10ポイント」
「和文所属 7ポイント」、「英文所属 7ポイント」
e)変数は斜体、定数は立体に書くことが望ましい。
f)数字の添字は印刷仕上がりで十分に見える程度の大きさとする。 |
|
(4) |
図・表・写真
a)図・表は印刷仕上がりで十分判読できるよう、鮮明かつ適当な濃度で作成する。
b)内容および凡例の文字・記号は印刷仕上がりで十分に判読できる大きさとする。
c)カラー写真をモノクロとして使用する場合は、明暗がはっきりしないことがあるので注意する。 |
| 3.論文および報告の構成 |
|
論文および報告の構成は下記による。質疑討論はこれに準ずる。 |
| (1) |
表題と氏名 |
|
(2) |
英文要旨(Abstract) |
|
(3) |
キーワード(Keywords) |
|
(4) |
本文(本文は図・表・写真を含め、下記を標準とする)
a)まえがき(Introduction)
b)本論(Body)
c)結語(Conclusion)
d)謝辞(Acknowledgement) |
|
(5) |
付録(Appendix)、注(Notes)および参考文献(Re-ferences) |
|
(6) |
英文要約(Summary)または和文要約(書き方種別B・Cの場合のみ) |
|
(7) |
所属機関・学位 |
| 4.表題と氏名 |
| (1) |
表題は書き方種別A、B、Dのときには、和文表題を先に、その下行に英文表題を、書き方種別C、Eのときには英文表題を先に、その下行に和文表題を記載する。氏名の場合も同様順序とする。 |
|
(2) |
大会学術講演会または本会事業の研究発表の場あるいは報告書で発表されたものはその発表場所・時期を注記する。 |
|
(3) |
表題は論文、報告および質疑討論の内容を具体的に表現したものとする。 |
|
(4) |
表題・氏名欄等の取り方は以下による。
a)表題および氏名欄は第2行目から概ね15行目までの範囲で、上下に十分な空白行を取り、なるべく中央に割り付ける。
b)表題と氏名の間には2行程度の空白行を挿入する。
c)英文表題はすべてを大文字で記入する。
d)英文氏名は、名を先に姓を後に書く。名は先頭文字のみ大文字とし、姓はすべてを大文字とする。
e)各人の氏名には「所属機関・学位」記入との対応を示す肩付き記号をつける。(1名の場合は不要)/TD>
|
| 5.英文要旨 |
| (1) |
論文の内容の主要な点を100ワード以内に簡潔にまとめ、氏名の後に記載する。 |
|
(2) |
氏名との間は本文1行以上の空白行を挿入する。 |
|
(3) |
英文要旨は、原稿用紙の左右に本文相当2文字ずつの空白をあけて、なるべく中央に割り付ける。 |
| 6.キーワード |
|
キーワードは文部省学術用語集から英文および和文のそれぞれについて3〜6語を選択する。
a)キーワードは英文要旨の後に記載する。
b)英文要旨との間は本文相当1行以上の空白行を挿入する。
c)キーワードは、原稿用紙の左右に本文相当2文字ずつ空白をあけて、なるべく中央に割り付け、1語ずつカンマで区切って記入する。
d)記入順序は英文を先行に、和文を後行に記入する。
e)英文キーワードはイタリック体(斜体字)とする。
f)キーワード記入欄と本文との間に1行以上の空白行を挿入する。 |
| 7,所属機関・学位 |
|
論文および報告の発表者全員の所属機関、役職、学位(和文名、英文名)を明記する。
a)所属機関・学位は文末に記入する。
b)記入に先立ち、本文との間に罫線を引く。
c)記入は著者名に対応する肩付き番号、所属機関と職位、次いで学位を記入する。
d)記入は和文を左側に、英文を右側に全員の各項目の先頭位置を揃えて記入する。
e)和文の所属機関と職位の間は1文字空け、職位と学位の間は「・」を記入する。 |
| 8.本文 |
| (1) |
本文の書き方
a)和文の文体は口語体とし、原則として常用漢字・新かなづかいを用い、用語はなるべく学術用語とする。
b)ローマ字、アラビア数字、ギリシャ文字、上ツキ、下ツキ、大文字、小文字などまぎらわしいものは特に注意を払うこと。
c)図・表・写真の横には、原則として本文は組まない。 |
|
(2) |
数式
数式には、(1)、(2)、(3)などと通し番号を付す。 |
|
(3) |
図・表・写真
a)図表は直接掲載位置に貼り込む。
b)デジタル写真などは直接掲載位置に貼り付ける。
c)アナログ写真は原稿に直接貼り付けるとともに、プリント写真の裏面に代表者名を記入したものを1枚別添する。なお、ネガフィルムは受け付けない。
また、写真の中に直接説明文が入る場合は、写真に直接タイプ文字を貼り込む。
d)図・表・写真には、内容を明確に表す表題を必ず付けること。
e)書き方種別Bの場合の図表等の表題は英文で記載すること。
英文表題の書き方は、初語の頭文字のみを大文字とし、その他は小文字を用いる。ピリオドは省略する。
f)表題には、図・表・写真ごとに通し番号を付ける。この時、章毎に分けずに図1、図2、・・、表1、表2、・・、写真1、写真2、・・、などと記入する。
英文表題の場合は、Fig.1、Fig.2、・・、Table.1、Table.2、・・、Photo.1、Photo.2、・・、などと記入する。
g)表題記入位置は、図・写真の場合その真下、表の場合はその真上とする。 |
|
(4) |
組み方
a)章と章の間は2行の空白行を挿入する。
b)各段落の最初は1文字分の空白を挿入する。
c)図・表・写真と本文の間は1行以上の空白行を挿入する。
d)図・表・写真の横には原則として本文を組み込まない
e)注および参考文献の番号は、本文の引用箇所に肩付き文字1)、2)のように明記する。 |
| 9.注および参考文献 |
| (1) |
注および参考文献は、本文の後にそれぞれを使用順に番号を付け、まとめて掲載する。 |
|
(2) |
参考文献の記載方法は以下の通りとする。
a)論文等の場合は「著者名:表題、誌名、Vol.、No.、掲載頁、発行年月」の順とする。
b)単行本の場合は「著(編)者名:書名、発行所名、発行年」の順とする。
c)著者名は必ず姓名で記す。著者が多い場合には、筆頭者以外は「ほか○名」で省略することもできる。
d)欧文の場合には、筆頭者は姓を先に記す。また連名者は「et al.」で省略することもできる。
e)発行年月は、原則として西暦で「1995.1」「1995.2」のように記す。 |
|
(3) |
一般に公表されていない文献、たとえば未発表の論文、簡易印刷(コピーしたものなど)の委員会報告や社内報告および私信などは、文献として扱わない。必要があれば注とし、引用箇所に肩つき注1)、注2)のように明記する。 |
|
(4) |
図・表・写真などの引用・転載にあたっては、著者自身が原著者などの著作権所有者の許可を取らなければならない。 |
|
(5) |
注および参考文献は1行(1段)35文字で記入する。 |
|
(6) |
脚注・参考文献記載後の論文末尾に「原稿受理日・採用決定年月日」(採用決定後、本会で貼付)の余白を2行程度空ける。 |
| 10.英文要約または和文要約 |
| (1) |
原稿書き方種別が、BまたはCの場合は、英文要約または和文要約を論文の末尾に付ける。 |
| (2) |
英文要約は1,600語以内とする。また、和文要約は5,000字以内とする。 |
| (3) |
要約中には図表を挿入せず、本文図表の参照引用にとどめる。
a)書き方種別がBまたはCの場合、英文要約または和文要約を上記の論文記入後の末尾に記入する。
b)記入に先立ち、本文・注および参考文献記載後罫線を引き、さらに本文相当1行以上の空白行を空けて記入する。
c)記入に先立ち、表題として英文要約はSummary、和文要約は「和文要約」の表題を1行使用して記入する。 |
| 11,質疑討論の書き方 |
|
ページ数
質疑討論・回答ともに所定原稿用紙2枚以内であり、超過ページは認められない。
2)表題
a)討論の場合は、第1行目に「討論対象の論文表題名」を、討論第2行目にカッコ付きで著者名・掲載論文報告名・号数・掲載年月を記入する。
b)回答の場合は、討論者(全員の氏名記入)への回答を記入する。
3)討論・回答ともに全員の氏名を記入する。 |
| 12.データベースへの登録について |
|
採用された論文、報告および質疑討論は、国立情報学研究所における「NII論文情報ナビゲータ」のデータベースに登録する。 |
| (1) |
データベース著作権は、本会および国立情報学研究所の共有とする。 |
| (2) |
本データベースは国内外で検索できる。 |
| 13.その他 |
| (1) |
不備な原稿等の返却
応募規定、本執筆要領の下記に示す事項を守っていない原稿は事務的に返却する。
a)既発表の論文
b)連続した論文の先の編の査読が終了していないもの
c)応募資格者以外が著者になっているもの
d)頁数を超過したもの
e)原稿の記入枠・行数・字数等の規格や組み方が著しく異なるもの
f)図・表・写真等が版下原稿として作成されていないものおよび不鮮明なもの
g)文字の大きさと種別が適切でないものおよび印字が不鮮明なもの
h)提出原稿の部数・添付書類の不備なもの |
| (2) |
原稿の返却
論文集刊行後に「版下原稿」の返却を希望する場合は、その旨明記し、返信用封筒(角2封筒)に郵送料相当分切手を貼付し、論文集の発行月の月末本会事務局まで送付する。
期日までに、上記の返却手続のない原稿は破棄する。 |
| 付則 |
|
本要領は2005年2月7日より施行する。 |