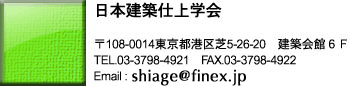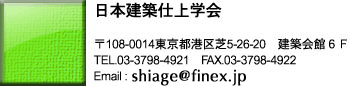|
| Home
> 会員情報 top > [過去]2022年終了行事 |
| 会員情報 2022年終了分 |
本学会の後援・協賛、会員による催し物のご案内などを掲載しております。内容については主催団体にお問い合わせ下さい。
ご不明な点は、日本建築仕上学会・事務局までお問い合せ下さい。 |
|
ここから下の項目の見学会・セミナーは終了しています。 |
| 会員情報 | 一般社団法人日本塗装技術協会 |
| 第5回プロフェッショナルセミナー 参加者募集 |
主催 一般社団法人日本塗装技術協会
協賛(依頼予定) 日本化学会、色材協会、日本塗料工業会、日本塗装工業会、表面技術協会、
日本塗装機械工業会、高分子学会、日本工業塗装協同組合連合会、日本自動車車体工業会、
日本防錆技術協会、材料技術研究協会、日本レオロジー学会、日本印刷学会、
日本建築仕上学会、日本塗料検査協会、日本油化学会、、腐食防食学会、自動車技術会、
静電気学会、粉体工学会、日本粉体工業技術協会、国際工業塗装高度化推進会議、
エポキシ樹脂技術協会、日本塗料商業組合 (順不同) |
| 「より深く本質的な、日々の課題にヒントを与えてくれる塗装技術の話を聴きたい!」 |
そんな会員の熱い声に応えて誕生したのが「プロフェッショナルセミナー」です。
一昨年、2020 年11 月6 日、プロフェッショナルとして活躍されている塗装技術者、塗料技術者を対象として、第1回プロフェッショナル セミナーを開催いたしました。(一社)日本塗装技術協会にとって初めてのオンラインライブ形式での開催でしたが、通常の講演会の3倍程度の時間を掛けて分かり易くお話しいただき、Q&A タイムも1時間近く確保した結果、大変好評を博しました。昨年度の第2回、第3回に引き続き、本年8月5日に第4回プロフェッショナルセミナーを開催いたしました。
来たる12月2日,金曜日,13時~16時45分、オンラインライブ形式で第5回プロフェッショナルセミナーを開催します。テーマは、「欧州自動車技術国際会議に見る、塗装技術動向」、講師は自動車メーカーで41年間、技術コンサルタントとして7年間、塗装生産技術一筋に活躍なさって来た田村吉宣さんです。
自動車塗装に携わっている皆さんは勿論、塗装のあるべき姿を考え、追求なさっている皆さんに是非聴いていただきたい内容です。
なお、本セミナーでは、本番当日2週間以上前にテキストをお送りします。事前の質問、当日セミナー中の質問、事後の質問も大歓迎です。皆さま奮ってご参加願います! |
| プロフェッショナルセミナー実行委員長 奴間伸茂 |
日 時 : 2022年12月2日(金) 午後1 時から午後4 時45 分まで
会 場 : オンライン開催(詳細については決定次第ホームページ等でお知らせいたします)
「Zoomビデオウェビナー」で行います |
テーマ :欧州自動車技術国際会議に見る、塗装技術動向
《講師》田村 吉宣 氏
久保井塗装株式会社 塗装改善研究室 室長 |
<要 旨>
塗装技術動向‥誰しもが知りたい事であろう。しかし範囲は広大で業界も調査方法も迷う。この一つの回答は人・物・金が集まり凌ぎを削る頂点業界の自動車塗装についての国際会議調査である。
約15年前「25年以上を経過した自動車塗装工場の老朽代替・生産統合・新鋭化を同時達成する計画を立案せよ。」との上位指示が下り「まずは世界最新鋭の自動車塗装工場を見学しよう。」という事になり、中国長春第一汽車の2工場を見学した。そして驚愕した。そこでは、想像を絶するドイツ製の未来塗装工場が実在し、稼働していた。日本技術の周回遅れと「先端塗装技術は欧州に在り」を思い知らされた瞬間であった。
かくして2008年以来、欧州の2つの自動車塗装技術国際会議(SurCar、Berlin)に参加し、2日間にわたる欧米スター塗装技術者達の膨大な最新発表を定点調査して来た。不肖私もベルリンで2回、パリで1回の発表を行う幸運に恵まれたものの、欧州の目が眩むような先端技術に圧倒され、自動車塗装技術のデファクトスタンダードが確立されて行く様に憧憬を抱いた。
本セミナーでは15年にわたる国際会議の内容と変遷を俯瞰し「塗装技術の過去・現在・未来」を共有し、日本工業塗装の今後のあるべき姿について闊達な論議を交わしたい。 |
<内 容>
1.欧州自動車塗装技術国際会議の紹介
2.2008年~2014年の国際会議トピックス
3.2015年の転換点
4.欧州と日本の差異分析
5.2021年SurCar(カンヌ)の概要
6.2022年Berlin の概要
7.欧州自動車塗装技術国際会議に見る「工業塗装技術の過去・現在・未来」 |
注意事項
*無料アプリを使用して、ウェブ配信により開催します。
(視聴するウェブサイトは午後0 時30 分からオープンします)
詳細につきましては後日、直接連絡いたします。
*受講に際して、
1.受講者が、本セミナーの内容を録画・キャプチャーすることを禁止します。
もし、発見した場合、事務局は削除を要求できることとします。
2.また、SNS などへのアップも禁止します。
セミナーの内容や受講者の個人情報などはセミナー内のみとし、口外しないでください。
3.システムトラブルなどにより、画像・音声に乱れが生じた場合も対応出来かねますので
ご自身でご調整ください。
4.配信中、異常と思われる接続を発見した場合、予告なく切断することがあります。 |
参加要領
参加資格・参加費 : 複数人申し込みの特典を設けました!
・日本塗装技術協会正会員 15,000 円 (正会員複数人申込特典 @12,000 円)
・非会員 20,000 円 (非会員複数人申込特典 @16,000 円)
※複数人申し込みは、代表者が一括して申し込みください
※不明の点は事務局までお尋ねください
・当オンラインイベントは、お申込みいただいた参加者1 名のみ参加が可能です。
(申し込みをいただいた個々人宛にご案内します)
★複数人申し込みをされない方が同席して視聴することを禁止します。 |
申込方法 : お申し込みはホームページをご覧ください。
http://jcot.or.jp/
申込書にご記入の上、下記申込先へ原則として電子メール添付にてお送り下さい。
★お申込み後のキャンセル・返金は 一切お受けできません。代理の方の参加をお願いいたします。
欠席の方には資料を送付し、出席と替えさせていただきます。
★申込の前に、Zoom へのアクセスに支障がないことをご確認ください
(http://zoom.us/test) |
申込先 : 一般社団法人日本塗装技術協会 事務局 〒162−0805 東京都新宿区矢来町3 番地
E-mail:tosou-jimukyoku@jcot.or.jp TEL:03-6228−1711
振込先 : 郵便振替 00110-9-77544 名義 一般社団法人日本塗装技術協会
銀行振込
三菱UFJ 銀行 神楽坂支店 普通口座 0578987 名義 一般社団法人日本塗装技術協会
三井住友銀行 飯田橋支店 普通口座 7257841 名義 一般社団法人日本塗装技術協会
(★振込手数料は振込人にてご負担いただきますようお願いいたします。) |
|
| →詳細と申込書 |
|
| 2022.9.16 |
|
| 会員情報 | 一般社団法人 日本建築学会 |
| 講習会「建築物の耐久設計支援ガイドブック」 |
日 時:2022年10月12日(木)
場 所:建築会館ホール
オンライン(リアルタイム動画配信(クラストリーム))
申込締切り:2022年10月2日(日)【建築CPD申請中】
(日本建築仕上学会 後援行事) |
|
| →詳細と申込書 |
|
| 2022.8.10 |
|
| 会員情報 | 一般社団法人 日本塗装技術協会 |
2022 年度 第2回講演会
「塗料塗装分野の評価の数値化と DX を目指して 」
塗装と評価 ~数値化、デジタル化、プロセス管理~ |
日本塗装技術協会では自動車、建造物、橋梁、家電製品等のあらゆる分野の塗料・塗装に関する技術的な問題を扱う技術者、研究者に情報交換の場を提供し、我が国のコーティング技術の発展に貢献しています。
塗料・塗装業界での塗装とその評価における数値化、デジタル化は、品質問題解決、低コスト化、環境負荷低減を実現する今後の重要なアイテムです。また、更なる競争力強化のためにはDX( デジタルトランスフォーメーション) を加速する必要があります。
そこで本講演では、画像センシングへのAI 活用、視覚的評価技術、塗装欠陥の新たなものさし、塗装ラインのIoT 化、VR空間での塗装シミュレーション等の最先端技術についてご紹介いただきます。また、当日はウエブ上での講演とさせていただきますが、口頭での質疑応答を基本にZOOM のQ&A を利用した質問も可能です。ぜひともこの機会をご活用いただき、皆様方の今後の発展に役立つものとなれば幸甚に存じます。 |
| セミナー委員会 実行委員長 莊司 浩雅(日本製鉄㈱) |
主 催:(一社)日本塗装技術協会
後 援:日本化学会、色材協会、日本塗料工業会、日本塗装機械工業会、高分子学会、
日本工業塗装協同組合連合会、日本自動車車体工業会、日本防錆技術協会、
材料技術研究協会、日本レオロジー学会、日本印刷学会、日本建築仕上学会、
日本塗料検査協会、日本油化学会、腐食防食学会、自動車技術会、静電気学会、
日本粉体工業技術協会、国際工業塗装高度化推進会議、エポキシ樹脂技術協会
(順不同)(予定)
日 時:2022 年11 月18 日(金)9:50 ~ 16:15
会 場:オンライン開催(ZOOM)
詳細につきましては後日、参加者に直接連絡いたします。
プログラム:
09:50 開会の挨拶とガイダンス
日本塗装技術協会 第2回講演会実行 委員長
10:00 ~ 11:00 「画像センシングの基盤とAIによる高度化技術」
慶應義塾大学 理工学部 教授 斎藤英雄
11:05 ~ 12:05 「粉体塗料、自動車内装の総合評価装置spectro2profiler」
ビックケミー・ジャパン㈱ ガードナー測定器部 部長 永江勇二
昼食休憩(55 分間)
13:00 ~ 14:00 「塗装欠陥見本とその「ものさし」の標準化」
コニカミノルタ㈱ 外観計測事業推進部 グループリーダー 吉田龍一
14:05 ~ 15:05 「塗装ラインのIoT 化を実現するBDACS エッジコンピューティング」
㈱バルクケミカルズ・ジャパン 代表取締役 手嶋律夫
15:10 ~ 16:10 「VRシミュレーターによる塗装教育のDXについて」
㈱ブロードリーフ 特販部 課長 吉田幸徳
16:10 ~ 16:15 閉会の挨拶と今後のご連絡
※各講演の間に5分間程度の休憩時間を設けました。
(但し質疑応答等で若干時間が変わる場合があります。)
講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。
参加 費:日本塗装技術協会及び協賛学協会 会員16,500 円、
非会員22,000 円、学生参加者3,300 円
(振込手数料は振込人にてご負担いただきますようお願いいたします。)
申込方法:申込書をこちらのページ(http://jcot.or.jp/kouenkai2022-2.html)から
ダウンロードして、ご記入のうえ、メール(E-mail: tosou-jimukyoku@jcot.or.jp) に添付してお申し込みください。
★お申込み後のキャンセル・返金は 一切お受けできません。
代理の方の参加をお願いいたします。
★申込の前に、Zoom へのアクセスに支障がないことをご確認ください。
(http://zoom.us/test)
お問合せ:(一社)日本塗装技術協会 事務局
〒162-0805 東京都新宿区矢来町3 番地
E-mail:tosou-jimukyoku@jcot.or.jp TEL03-6228-1711
お申込み受け付け次第、ご案内と請求書を送付いたします。 |
|
| →詳細と申込書 |
|
| 2022.9.16 |
|
| 会員情報 | (一社)日本建築ドローン協会(JADA) |
第11回 建築ドローン技術セミナ-
「マイクロドローンの活用とJADAガイドライン(案)の概要」開催のご案内 |
| 建築分野におけるドローン活用領域は屋外と屋内空間に大きく分けられており、屋内空間では狭所空間(天井裏、床下、EVシャフト等)におけるマイクロドローンによる調査方法への期待が高まっています。このような社会的要請に対応するため、当協会ではマイクドローン活用セミナー第2弾として、本技術セミナーを企画致しました。
JADA建築狭所空間ドローン利活用WGが作成した「建築狭所空間ドローン利活用実施ガイドライン(案)」もご紹介いたします。 |
| 記 |
【後 援】日本建築仕上学会
【主 催】(一社)日本建築ドローン協会(JADA) |
【日 時】 2022年11月18日(金)13:30-17:00(オンライン受付:13時から)
【講習形式】 Zoomによるオンラインライブ配信
【セミナー詳細、申込情報掲載URL】 https://jada2017.org/news/notice/1560
【会 費】JADA日本建築ドローン協会会員3,000円(税込)/1名
後援団体会員6,000円(税込)/1名
※当会会員様は後援団体会員料金の適用となります。
非会員(一般)12,000円(税込)/1名
※セミナー資料を含む |
【申込〆切】2022年11月11日(金)17時まで(定員100名になり次第締め切ります)
本セミナーに関するお問合せは、下記へお願いいたします。 |
【JADA】
一般社団法人 日本建築ドローン協会 事務局
Mail: info@jada2017.org Tel: 03-6260-8655 |
|
| 2022.9.27 |
|
| 会員情報 | (一社)日本建築ドローン協会(JADA) |
【JADA】第10回 建築ドローン技術セミナ-
「ドローンにつながるNext Innovation」開催のご案内 |
建築分野においてもドローンの導入・活用が検討され、様々な研究領域から自治体に至るまで横断的に展開されています。本セミナーでは、建築ドローンに関わるイノベーションのヒントとなる研究組織や自治体の取り組みに焦点を当て、第10回技術セミナーとして企画いたしました。具体的には、国交省が進めるRCマンションのインスペクションDX、つくば市によるスーパーサイエンスシティ構想、ドローンを利用したインフラ点検の取り組み、ドローンと3次元計測技術、そしてドローン技術の動向と今後の方向性について情報提供することを目的としております。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。 |
| 記 |
【後 援】日本建築仕上学会
【主 催】(一社)日本建築ドローン協会(JADA)
【講習形式】Zoomによるオンラインライブ配信
【日 時】2022年9月28日(水)13:30-17:00(オンライン受付:13時から) |
【講演内容】
13:30-13:35 挨拶 (一社)日本建築ドローン協会副会長 宮内 博之 氏
講演① 13:35-14:15
「RCマンションのインスペクションDXに向けて」
国土交通省 国土技術政策総合研究所 建築研究部 材料・部材基準研究 室長
三島 直生 氏
講演② 14:15-14:55
「つくばスーパーサイエンスシティ構想」
つくば市 政策イノベーション部 スマートシティ戦略課 課長補佐
大垣 博文 氏
講演③ 14:55-15:35
「ドローンを利用したインフラ点検の取り組み」
東北大学 未来科学技術共同研究センター 産業連携促進研究プロジェクト 教授
大野 和則 氏
講演④ 15:45-16:25
「ドローンと3次元計測技術と建築の情報化に関する考察」
早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 建築学科 准教授
石田 航星 氏
講演⑤ 16:25-17:00
「建築分野におけるドローン技術の動向と今後の方向性
建築研究所 材料研究グループ 上席研究員
宮内 博之 氏
17:00 閉会
※講演題目は、状況により変更する可能性がございます。 |
【会 費】
JADA日本建築ドローン協会会員3,000円(税込)/1名
後援団体会員6,000円(税込)/1名 ※当会会員様は後援団体会員料金の適用となります。
非会員(一般)12,000円(税込)/1名
※セミナー資料を含む
【定 員】100名(先着順) |
【申込方法】
1.下記の「オンラインセミナー受講規約」をご確認ください。
本セミナーは申込みを頂いた段階で、受講規約へ同意して頂いたと判断させて頂きます。
https://jada2017.org/wp- content/uploads/2021/02/ae08d2b035b39941272dbea4ce52b8f7.pdf
2.下記「申込フォーム」よりお申込みください。
最初に「後援団体会員様」のボタンを選択してください。
https://jada2017.org/moushikomi
「所属先後援団体」は、プルダウンより当会をご選択ください。
3.お申込と同時に会費を下記指定口座までご入金ください。
【振込先口座】
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 2408701
一般社団法人日本建築ドローン協会
【申込〆切】
2022年9月16日(金)17時まで(定員になり次第締め切ります。) |
【情報掲載URL】
https://jada2017.org/news/events/1512
*Zoomアクセス情報及びセミナー資料については、
セミナー開催1週間前を目安にお申込のEメールへご案内いたします。
本セミナーに関するお問合せは、下記へお願いいたします。 |
【JADA】Japan Architectural Drone Association
一般社団法人 日本建築ドローン協会 事務局
Mail: info@jada2017.org Tel: 03-6260-8655 |
|
| |
|
| 2022.8.22 |
|
| 会 告 | (一社)日本防錆技術協会 |
第42回防錆防食技術発表大会
大会参加者募集のお知らせ |
実行委員長 濵田秀則
第42回防錆防食技術発表大会は、令和4年7月5日(火)、6日(水)に東京・御茶ノ水の「東京ガーデンパレス」で開催されます。
当発表大会は、実務に役立つ現場技術から応用と、幅広い防錆防食技術の発表が行われております。様々な分野で利用され、確たる防錆防食技術を広めるためにも発表をいただき、本大会が技術交流及び情報収集の場として活用でき、さらに充実した大会になるよう努力していきたいと考えております。
現在、防錆防食に関する技術発表及び腐食事例(と対策)、製品・施工技術発表を募集しております。本発表大会は、毎年、多数のご参加を得て、おかげさまで42回を迎えることが出来ました。今回もふるってご発表、ご参加下さいますようお願い申し上げます。
また、例年同様、”若手技術者優秀発表賞”を設けましたので、ご応募をお待ちしております。
|
| 記 |
1. 会 期 令和4年7月5日(火)~6日(水)
2. 会 場 東京ガーデンパレス、2階 高千穂
JR・中央線 御茶ノ水駅 聖橋口より徒歩 5分
東京都文京区湯島1−7−5
tel 03−3813-6211
3. 発表区分
① 技術発表(施工事例を含みます)
② 腐食事例(と対策)
③ 製品・施工技術発表(詳細は別紙 製品・施工技術発表をご確認下さい。)
4. 発表資格等
(1) 発表資格 発表資格は問いません(会員及び会員外)
(2) 発表時間 ① 技術発表:発表15分、質疑5分
② 腐食事例(と対策):発表12分、質疑3分
③ 製品・施工技術発表:発表14分、又は7分、質疑なし
(3) 発表申込締切 令和4年3月18日(金)
(4) 予稿原稿締切 令和4年5月11日(水)
5. 発表方法 Power Point又はPDFをご利用下さい。
6. 申込方法 申込書をFAX又は、Emailを利用してお申し込みください。
[FAXの場合] 様式1の申込書に必要事項をご記入の上、
250字以上300字以内の要旨を添えて当協会あてに
FAX(03-3434-0452)にてお申し込み下さい。
[Emailの場合] 下記のメールアドレスに発表申込書希望とご記入の上
ご送信下さい。返送メールにより書式を添付致しますので、ご記入の上、
送信して下さい。
メールアドレス jacc@iacc1(イチ).or.jp 日本防錆技術協会
[確 認] 申込書の受領は、1週間ほどで確認のお知らせをいたします。
7. 発表予稿原稿 A4版用紙2,4又は6頁にワープロで作成し、PDFに変換して、5月11日までにご送付下さい。
メール又は郵送でお送りください。PDF変換後の内容を必ずご確認下さい。
発表予稿原稿は、聴講者に理解しやすいように、下読みをさせていただきます。
(予稿作成要綱は、申込受付後、順次送付いたします。また、予稿集はPDF画像としてCD-ROM版としても作成いたします。)
8. 若手技術者優秀発表賞
防錆防食技術発表大会では、第33回より防錆防食分野の発表で、分かりやすい技術発表をした若手技術者(4月1日現在39歳以下)に対して、「若手技術者優秀発表賞」を授与することになりました。
当協会若手技術者優秀発表賞審査委員会による厳正な審査(予稿集はわかりやすいか、発表時間の厳守、パワーポイントの文字や図表のみやすさなど。)の上、受賞者を選びます。受賞者には、実行委員長名の賞状及び副賞を贈呈いたします。
ただし、受賞候補者となるには、事前の申請が必要ですので、ご注意ください。
「若手技術者優秀発表賞」の受賞は、次の条件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 本協会の個人会員又は候補者の所属する団体が正会員、又は協賛学協会会員であること。
(ただし、入会手続き中の者は会員とみなします。)又は防錆管理士、大学生、大学院生であること。
(2) 発表大会開催年の4月1日において39歳以下で、本賞の受賞歴が2回以下である方。
(3) 技術発表の筆頭著者の方。
(4) 発表申込みに本賞候補者として事前申請している方(発表申込書にご記入ください)。
(5) 発表予稿原稿を、A4版用紙4又は6頁で作成した方。
(6) 防錆防食技術発表大会に参加登録し、かつ実際に発表された方。
|
9. 会 費
区分前納*
(令和 4年 6月27日(月)まで) 令和 4年 6月28日(火) ~当日
当協会会員** 16,000(円) 18,000(円)
協賛学協会会員 16,000(円) 18,000(円)
一 般 20,000(円) 22,000(円)
学 生 5,000(円) 5,000(円)
(*:一般参加申し込みは、令和4年5月2日より受付を開始致します。)
(消費税10%含む)
(**:正、法人・個人賛助、防錆管理士会会員)
発表大会でのご発表につきまして、ビデオ撮影、写真撮影、録音などは、禁止します。
会場内でのPCの使用は休憩時間のみとし、発表中の使用は禁止します。
10. 申込問い合わせ先
〒105−0011 東京都港区芝公園3−5−8
一般社団法人日本防錆技術協会 第42回防錆防食技術発表大会事務局
TEL 03-3434-0451 FAX 03-3434-0452 Email:jacc@jacc1(イチ).or.jp |
| 詳細はこちら→pdf |
FINEX 2022.5-6 |
| 会 告 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) |
新時代Active Materials
自己治癒するセラミックス・金属— その特性と応用 |
| URL: https://www.kistec.jp/tearn/researcher/jikochiyu/ |
1.開講期間 令和4年6月30日(木)7月1日(金) 計2日間
2.募集人員 15名
3.開催場所 Zoomによるオンライン講座
4.受講料 37, 000円(全日程)/22, 000円(1日受講) |
5.主な対象 企業、研究機関にご所属で、新しい材料の研究開発や機械設計に携わる方
高機能表面の創製を目指す方
複合加工などにより、材料の新しい産業領域への展開を目指す企業の方
・・・メーカー・ユーザーいずれの方も承ります
6.カリキュラム編成・監修 国立大学法人横浜国立大学 |
7.主催 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)
|
8.後援 (公社)日本金属学会 (公社)日本材料学会 (—社)日本機械学会
(—社)日本トライポロジー学会 (公社)日本ガスタービン学会 (—社)日本計算工学会
(公社)日本表面真空学会 (—社)日本複合材料学会 (—社)日本建築学会 日本ばね学会
川崎商工会議所 (—社)軽金属学会 (公社)自動車技術会 (公社)日本セラミックス協会
(—社)ターポ機械協会 (—社)日本鋼構造協会 日本建築仕上学会 耐火物技術協会
(—社)日本ファインセラミックス協会 (—社)日本熱処理技術協会(株)ケイエスピー
<一部申請中> |
| 詳細はこちら→pdf |
2022.6.6 |
| 会員情報 | 一般社団法人色材協会 関東支部 |
| 第62回 「塗装入門講座」 |
日時 前期日程:2022年6月16日(木)9:30~16:50、
17日(金)9:3.0~16:50
後期日程:2022年7月14日(木)9:30~16:45
15日(金)9:30~17:00
場所 東京大学 生産技術研究所(駒場リサーチキャンパス内An 棟) コンベンションホール
〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1
小田急線・東京メトロ千代田線/代々木上原駅より徒歩15 分
小田急線/東北沢駅から徒歩10 分
京王井の頭線/駒場東大前駅西口から徒歩15 分
京王井の頭線/池ノ上駅から徒歩15 分 |
|
| →詳細と申込書 |
|
| 2022.5.2 |
|
会員情報 | (一社)日本非破壊検査協会 RC構造物の非破壊試験部門 |
2022年度第1回 鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験部門
「極限劣化構造物の保存とアーカイブス化のための非破壊検査技術とは?」
ミニシンポジウム |
後 援:(公社)日本コンクリート工学会、(公社)土木学会
(一社)セメント協会、(一社)日本建築学会
日本建築仕上学会 |
表題の極限劣化構造物は端島(軍艦島)構造物群を意味します。右図にありますように,1916年に竣工された30号棟は崩落の進行が著しい状況にあります。このような極限劣化構造物は保存できるのか,撤去せざるを得ないのか,または他の手法があるのか,そこにはこの分野の技術の貢献できる解は未だに無いかも知れません。
この度,端島にて,オンラインにて,この島の構造物群の保存に向けた現状と今後の課題に対する情報共有のためのシンポジウムを企画させていただくこととなりました。最先端の研究の紹介とともに,島内の実況中継を兼ねた内容となっています。
非破壊検査協会の主催ということで,この壮大なテーマの窓口は非破壊試験を通したものとなりますが,今後多角的な的な視点で「極限劣化構造物の保存とアーカイブス化」を議論する起点になれば幸いと存じます。
奮ってのご参加をお待ちしています。 |
| 注)このミニシンポジウムでの受信映像や発表資料の保存(画面キャプチャを含む),録音,再配布は原則禁止です。必要な場合は,事前に発表者,ならびに主催者に許可を得てください。 |
日時:2022年4月25日(月) 13時00分~16時20分
開催方法:Zoomを利用したオンライン講演会
Zoomの使用方法等については参加申込を頂いた方にご案内いたします。
Zoom接続に必要なインターネット環境,PC,マイク*,カメラ* は
参加される方でご準備ください。
* PCに内蔵されている場合は不要です
参加費:
(一社)日本非破壊検査協会 鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験部門登録 団体会員
(一社)日本非破壊検査協会 鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験部門登録 個人会員
学生 無料
上記以外の方 ¥1,000円
定員:120 名「オンライン開催(運営のため、幹事数名のみ現地から参加)」
参加申込締切日:2022年4月11日(月) |
申込方法:協会ホームページ(https://sciences.jsndi.jp/rebar)からお申し込み下さい。
問い合わせ先:(一社)日本非破壊検査協会 学術課 蒲生
TEL (03)5609-4015, FAX (03)5609-4061, E-mail:gamou@jsndi.or.jp |
プログラム案:
13:00-13:10 開会挨拶 東京理科大学 今本啓一
13:10-13:50 講演1:長崎市役所 濵本和彦「国史跡端島炭坑跡の整備基本計画」
13:50-14:30 講演2:芝浦工業大学 濱崎仁「歴史的構造物のための非破壊試験」
14:30-15:10 講演3:建築研究所構造研究グループ 向井智久
「30号棟を対象としたGNSSによる長期計測と
損壊後の3Dスキャンから見えてきたこと」
15:10-15:25 休憩
15:25-16:20 島内実況中継視察(点線ルート:下記pdf参照)
16:20 閉会挨拶 日本大学 湯浅昇 |
| →詳細はこちら(pdf) |
|
2022.1.18 |
|
会員情報 | 一般社団法人 日本建築ドローン協会(JADA) |
第9回建築ドローン技術セミナー(予告)
建築ドローン関連の活用と最新動向 |
建築分野におけるドローンの環境整備も徐々に進んでおります。今回 、 国土交通省が進める3D都市モデル整備・活用・オープンデータ化のプロジェクトであるPLATEAUについて、本セミナーを通して最新情報を共有する場を設けさせて頂きました 。そして、建築分野におけるドローンの活用について、消防防災、施工・デジタル技術、そして点検調査における係留や新たな調査技術などの紹介を通して、今後の建築分野におけるドローン利用の可能性や方向性を感じて頂けるセミナー企画としました。
なお、本 セミナーの申込方法については、改めてご案内申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。 |
【名称】 第9回 建築ドローン技術セミナー
【主催】 (一社)日本建築ドローン協会 JADA
【後援 予定】(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会、(一社)住宅生産団体連合会、
(一社)ドローン操縦士協会、(一社)日本建設業連合会、日本建築仕上学会、
(一社)日本ドローンコンソーシアム、(一社)日本ドローン無線協会、
(一社)日本UAS 産業振興協議会、(一社)マンション 計画 修繕施工協会、
(公社)ロングライフビル推進協会 五十音 順
【講習形式】 Zoom による W eb セミナー
【日時】3月23日(水)13:30~17:00 オンライン受付:13時から)
【講演内容 】 挨拶 (一社)日本建築ドローン協会 副会長 宮内 博之 氏
①基調講演 3D都市モデルの活用によるスマートシティの社会実装の取組み
国土交通省 都市局 都市政策課 Project ”PLATEAU” チーム 企画専門官 大島英司 氏
②一般講演 消防防災分野におけるドロー利活用の現状と今後の展開
東京理科大学 理工学部 建築学科 教授 大宮喜文 氏
建築施工におけるドローンの活用
(一社)日本建設業連合会 建築本部生産委員会ICT推進部会
先端ICT活用専門部会 主査
((株)大林組 デジタル推進室デジタル推進第二 部 部長) 堀内英行氏
ドローン利用の安全技術 2点係留の実践
(一社)日本建築ドローン協会 理事 二村憲太郎氏
建築保全とドローン係留による新たな調査技術
東京理科大学理工学部 建築学科 教授 兼松学 氏
建物調査におけるドローン活用の動向と新展開
建築研究所材料研究グループ 主任研究員 宮内博之 氏
(※講演題目は 、状況により変更する可能性がございます。)
【参加費】日本建築ドローン協会会員 3,000円(税込)/1名、
後援団体会員 6,000円(税込)/1名、非会員12,000円(税込)/1名
(講演会資料を含む)
【定員】 100名(先着順) |
| →詳細はこちら(pdf) |
|
2022.1.13 |
|
会員情報 | 一般社団法人 日本建築ドローン協会(JADA) |
第14回 建築ドローン安全教育講習会【オンラインライブ配信】 |
【名称】建築ドローン安全教育講習会
【主催】一般社団法人 日本建築ドローン協会
【後援】(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会、(一社)住宅生産団体連合会、
(一社)ドローン操縦士協会、(一社)日本建設業連合会、
(一社)日本建築学会、日本建築仕上学会、
(一社)日本ドローンコンソーシアム、(一社)日本ドローン無線協会、
(一社)日本UAS 産業振興協議会、(公社)ロングライフビル推進協会 (五十音順)
【講習形式】Zoom によるオンライン座学講習(※スマートフォンでの受講は不可) |
【日 時】2 日間の講習
前半の部:2022年2月17日(木)13時30 分~17時10 分(オンライン受付13時~)
後半の部:2022年2月18日(金)13時30 分~17時00 分(オンライン受付13時~)
【開催方法】オンラインライブ配信
【対 象 者】建築物の施工管理、点検調査等におけるドローンの活用と安全管理に携わる者
(年齢20 歳(2021年4月1日時点)以上、資格・経験不問)
【C P D】建築CPD情報提供制度認定プログラム【5点】
【講習内容】ドローンの概論、法規、ドローン技術と安全運用、
ドローンを活用した建築物の施工管理、点検調査等における安全対策
【受 講 料】日本建築ドローン協会会員2万円(税込)/1名、
後援団体会員3万円(税込)/1名、非会員4万円(税込)/1名
(教材:「建築物へのドローン活用のための安全マニュアル」を含む)
【有効期限】2024年3月迄(修了証の更新期限を設定)
【定 員】50名(先着順)
【申込〆切】2022年2月3日(木)まで(定員になり次第締め切ります。)
【申込方法】①別紙、受講申込用紙に必要事項を記入の上、JADA 事務局までメールまたは
郵送して下さい。
メールの場合は、申込用紙とは別にJPG 形式の顔写真データをご提出ください。
郵送の場合は、受講申込用紙の所定欄に写真を貼付してください。
②申込みと同時に受講料を下記指定銀行へお振込みください。
③お申込みが完了した方にはメールにて「申込完了通知」をお送りいたします。
※一旦納付された受講料は返還されません。
【申 込 先】〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-6 徳力本店ビル 7 階
一般社団法人 日本建築ドローン協会事務局 E-mail: jimu@jada2017.org
【お振込先】銀行名:みずほ銀行(銀行コード0001)、支店名:神田駅前支店(店番号009)
口座番号:普通 2408701 口座名義:一般社団法人日本建築ドローン協会
(振込み手数料はご負担願います。)
【お問合せ】TEL:03-6260-8655 FAX:03-6260-8656 E-mail: info@jada2017.org |
| →詳細はこちら(pdf) |
|
2021.12.20 |
|
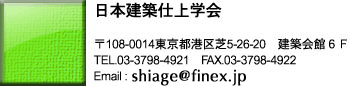
|